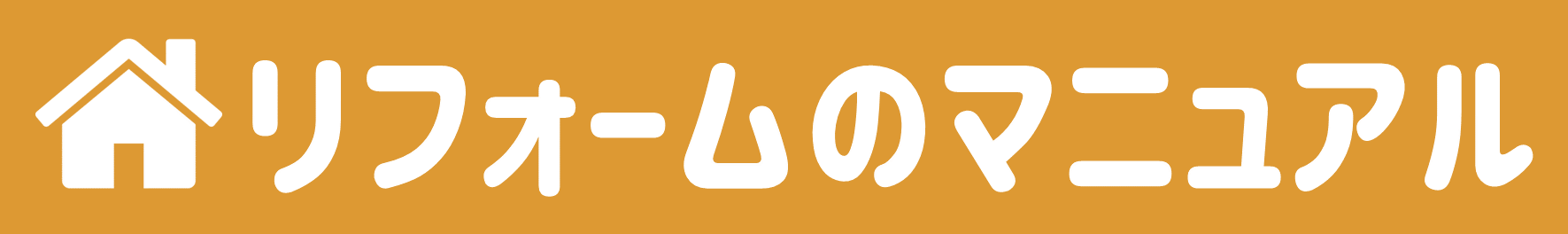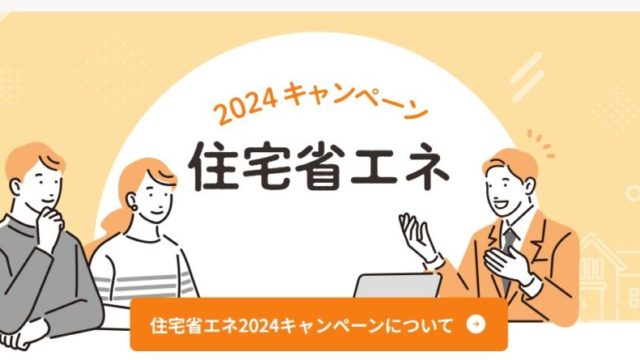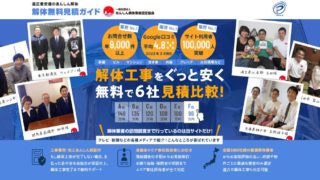・リフォーム瑕疵(かし)保険は義務ではなく任意の保険で、不具合を補修するための費用を保証するものです。
・業者が倒産した際の保証もあり、リフォーム完工時に保険会社の建築士による検査を受けることができます。
・申し込みは、審査を受けて登録されたリフォーム業者から行います。
・保険料が3~7万円位と高いため、あまり利用されていないのが現状です。
リフォーム瑕疵(かし)保険
リフォーム瑕疵(かし)保険とは
リフォームの保証する保険として「リフォーム瑕疵(かし)保険」というものがあります。
「瑕疵(かし)」とは欠陥、不具合といった意味で、「リフォーム瑕疵保険」はリフォーム時の検査と保証がセットになった制度で、 リフォームに関する欠陥工事から消費者を守るための保険です。
リフォームを行った後に、リフォーム工事の瑕疵(欠陥、不具合)が見つかった際に利用できる制度で、リフォーム工事の欠陥を補修する場合の費用や、リフォームを行った会社が倒産した場合もその費用を保証してくれるものです。
リフォーム瑕疵保険の取り扱いを行っているのは、通常の火災保険等の損害保険を扱っている会社ではなく、国土交通省から指定を受けた、下記の5社のみです。
- (株)住宅あんしん保証
- 住宅保証機構(株)
- (株)日本住宅保証検査機構
- (株)ハウスジーメン
- ハウスプラス住宅保証(株)
リフォーム瑕疵保険は義務なの?
リフォーム瑕疵保険は任意の保険で、義務ではありません。
施主が希望する場合のみ申し込めばいいものですが、個人で申し込む保険でもありません。
申し込みは登録業者から
リフォーム瑕疵保険への申し込みは、施主個人からではなく、事業者登録されたリフォーム会社から行います。
ですので、まずこの保険を使いたい時は、リフォーム会社が登録しているかを確認しないといけません。
リフォーム会社に聞いてもいいですが、下記の住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページで調べることも可能ですので、自分で確認してみましょう。
地元にある会社を検索することもできますし、リフォームの会社名で検索することもできます。
「商品の種類」は「リフォームかし保険」を選びましょう。
リフォーム瑕疵保険手続きの流れ
リフォーム瑕疵保険を利用する場合の流れを説明します。
保険への申し込み
リフォーム着工前に、申し込みます。
まずリフォームを依頼する施主(発注者)が、リフォームを依頼する会社に「リフォーム瑕疵保険」に加入してもらうよう依頼します。
保険会社による検査
リフォームが完成した後、保険会社の建築士による検査が入ります(工事によっては施行中の検査もあり)。
工事終了後
工事終了後に保険証書を発行してもらいます。
工事終了後、後日工事に欠陥が見つかった場合、補修のために必要な費用をリフォーム業者を通じて保険会社に請求してもらい、補修の工事をしてもらうことができます。
瑕疵が発見された時に、施工したリフォーム会社が倒産していた場合は、発注者が保険会社に直接補修のための費用を請求することができます。

リフォーム瑕疵保険のメリット
リフォーム瑕疵保険には、以下のメリットがあります。
リフォームの補修が必要な場合の保証
リフォーム終了時にその出来を確認して工事完了となるわけですが、その後何ら欠陥が見つかった場合、明らかに工事の不備によるもので、親切な業者なら対応してくれるかもしれません。
しかし工事は終了しているので更なる補修はやってもらえないか、追加の費用が必要である場合も多く、仕方なく諦めるか、追加の費用を払うことになります。
その点、リフォーム工事瑕疵保険に加入していれば、補修費用は保険会社から支払われるので、補修はスムーズに行われます。
リフォーム会社倒産の保証
リフォーム会社には小規模な会社も多く、価格などのメリットも多いのですが、どうしても経営的には大手よりも不安定で、倒産のリスクが高くなります。
その点、リフォーム工事瑕疵保険に入っていれば、依頼先の会社が倒産した場合でも保険会社に修繕費用を請求できるので、リスクが回避できます。
リフォーム会社の保証
前述のとおり、リフォーム工事瑕疵保険を利用するには、リフォーム会社が保険会社に事業者登録をしていなければいけません。
その登録には各保険会社が設けた基準があり、会社のリフォーム実績や事故が多かったりなど技術力が低い場合は登録できないなど審査を受ける必要があります。
リフォーム会社が瑕疵保険に登録されていれば、その審査を通っているので、ある程度の経験や技術がある会社だということが保証されます。
第三者による検査の実施
リフォーム瑕疵保険に加入しておけば、工事完了時に(工事によっては施工中にも)保険会社の検査員による検査が実施されます。
素人では工事の仕上がりを確認するのは難しいと思いますが、第三者である建築士の検査員により確実な仕上がりの確認をしてもらえるので、安心できます。
リフォーム瑕疵保険のデメリット
今までは制度のメリットばかりを挙げてきましたが、もちろんいいことばかりではなく、デメリットもあります。
保険料が高い
保険に入るためには当然ながら保険料を支払う必要があります。
保険料は施主側と施工者側どちらが払うとは明確には決まっていませんが、この保険は任意で、リフォームの依頼人である施主の希望で入るものですので、リフォーム会社が保険料を支払うことはまずなく、施主が負担することになります。
「リフォーム瑕疵保険登録事業者」などと言われると、何か自動的に申し込みしてくれそうですが、そうではなく費用もまず負担してもらえません。
保険料は内訳としては、純粋な「保険料」+「現場での検査料」になります。
リフォーム工事の費用の総額がいくらかにより保険料が変わってきますし、一般的なリフォームでは検査は終了時1回ですが、構造や防水に関する部分を含む場合は施工中にもおこなうので2回になります。
一般的なリフォームの一番安い100万円以下のリフォームの保険料+現場での検査料で30,000円程度します。
それから費用の総額により保険料が上がっていき、構造や防水に関するリフォームで2回検査を行うと、総額1,000万円程度の全体的なリフォームで70,000円程度します。
また増築もある場合は増床面積により金額が上がっていきます。
保険会社の一つ、(株)日本住宅保証検査機構(JIO)の保険料金表でいくらかかるか、確認してみましょう。
具体的な金額は2ページ目の保険料(ピンク)+検査料(ブルー)の合計になります。

保証期間が短い
上記の保険料で、「家の保険で費用が30,000円からだったら安いのでは」と思われる方も多いと思います。
この費用で10年も20年も保証してもらえれば安いと思いますが、この保険の保険期間は構造や防水に関する部分で5年間、それらを含まない一般的なリフォームでは1年間となっています。
1年間や5年間といった短期間でリフォームのやり直しが必要になるというケースは極めてまれで、ある屋根のリフォーム会社の話では「5年間で屋根の雨漏りがしたことは一度もない」、つまり一度もリフォーム瑕疵保険が必要だったことはないとのことでした。
工期が長引く
構造や防水に関するリフォームについては、通常で工事中検査と工事完了検査の2回の検査が必要、増築部分があれば別途検査が必要で、工期が長くなります。
また屋根の工事の場合、天候によって工事が予定通り進まない場合があるため、検査の日時の調整が必要になれば、さらに工期が長くなることがあります。
リフォーム瑕疵保険の現状は
上記のメリット、デメリットがありますが、実際の利用状況はと言いますと、保険料が割高なためあまり使われていない、というのが現状のようです。
もちろんリフォームで何百万もかかる場合で、保証してもらえるなら数万円余計にかかっても高くはない、という考え方の人は入ってもいいでしょうが、私個人的にはおすすめはしません。
では保証はどうするかというと、リフォームの契約書の中の請負契約約款にリフォームが契約通りでない場合の保証期間が2年、設備や内装については1年間など明記してあるはずですので、確認しましょう。
上記は補修してもらう場合ですが、会社が倒産の場合は、申し込む前に慎重に調べるのはもちろんですが、その他の方法としてはリフォーム会社紹介サイトが保証をしている場合もありますので、そちらを利用するのもいいと思います。
詳細は「リフォーム会社紹介サイトの保証について」で説明していますので、ぜひご覧ください。